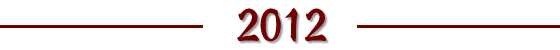1.七十二候を読み解く「雉始雎(きじはじめてなく)」
1.七十二候を読み解く「雉始雎(きじはじめてなく)」1月15日は雉が初めて鳴くという日。雄が雌を呼ぶというのですが、ケンケーンと勇ましい声で鳴くのが雄、雌はチョンチョンと優しげな鳴き声です。
父母(ちち はは)の しきりに恋し 雉子(きじ)の声 (芭蕉)
雉子の雌雄は大変仲むつまじいとされ、妻恋や親の愛情を雉子に託した和歌や俳句が多く詠まれました。雉は日本の国鳥で、1947年に定められました。元来北海道にはいなかったのですが、1930年頃から政府が放鳥し、全国に分布するようになりました。
雉は日本の古典に大変よく登場する鳥です。「古事記」の国譲りの場面で、下界に行ったきり帰らない神の迎えには誰が行くかということになり、雉が速く飛ぶのでふさわしいとして遣わされます。けれども矢で射られて死んでしまったことから、「キギシのひた使い」といえば、行ったきり帰らないことを言うようになりました。この時の雉の名は「鳴女」というのですが、別の場面ではその名の通り、弔いの場で泣く役割をふり当てられています。
また「雉も鳴かずば打たれまい」という諺は、口は災いの元と教えているわけで、雉の声は日本人にとってよほど印象的だったと思われます。平安期になると、貴族の狩猟の重要な獲物となり、肉の味も良いことから、何よりの御馳走として年中行事の食卓に供されました。以後中世までは鳥料理といえば雉のことだったそうです。しかしこうした人気は、棲息数を減らしていくことになります。かつて昭和初年くらいまでは、各地の耕地や草原で身近に見られたということです。