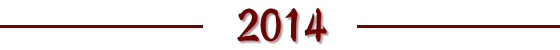門松は冥途の旅の一里塚
この格言は、下の句として「めでたくもあり、めでたくもなし」がつく狂歌で、一休禅師の作とされています。「一里塚」は街道に設けられた一里ごとの里程標。新年に玄関先に立てられる門松は、見ようによっては、着実にあの世へと向かう人生の里程標と言えなくもない。トンチ名人で炯眼な一休さんらしい句です。
さて、「明けましておめでとうございます」の「おめでとう」は「めでたい」が変化した言葉で、好み、愛する意ですが、これに接頭語の「お」をつけて「おめでたい」となると「おめでたい人だ」ときて、ばか正直とかお人好しといったマイナスイメージが強くなります。
実際、「めでたくなる」は「死ぬ」「倒れる」などの〈忌み語〉としても使われてきました。
注連縄は左縄に縒る…。
「しめ」はもともと「占める」の意で、「注連縄」は神が占める清浄な領域を示すとともに、不浄なものの侵入を防ぐために用います。「左に縒る」とは、普通の縄は右ねじりですが、注連縄は逆に左ねじりにして神聖さを表わしていることを示します。さて、この「注連」ですが、「心の注連」は強い気持ちを、「擂り粉木に注連」は不似合いなこと、「薬缶に注連縄を張る」は滑って張れないことから不可能なことを意味します。