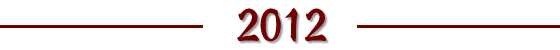2.七十二候を読み解く 「 黄 鶯 睨 皖 (こうおうげいかん) 」
2月9日は鶯が鳴き始めるという日。これを中国の七十二侯の暦では黄鶯睨皖といっています。
睨皖とは声や姿が美しいという意味です。それだけに昔から飼い鳥として尊ばれ、それぞれが飼っている鶯を持ち寄って、鳴き声の優劣を競う「鶯合わせ」という競技も行われました。美声とはいうものの、冬の間の鶯はチャッチャッという鳴き声で、これを笹鳴と呼びます。寒い時期は、人里に近い雑木林や藪で過ごしていますが、緑褐色なので枯れた草むらに溶け込んで人目につきにくいものです。鶯は日本全国に生息し、沖縄で二月上旬にホーホケキョの声を聞かれるのを皮切りに北上を始め、北海道で聞かれるのは四月下旬です。
今の世も 鳥は法華経 鳴きにけり ( 一 茶 )
経読鳥( きょうよみどり )は 鶯 の別名です。他にも春告鳥( はるつげどり )・花見鳥( はなみどり )・歌詠み鳥( うたよみどり )などと呼ばれています。春の代表的な鳥として、夏のほととぎすと並びます。
昔、男に助けられた鶯が、女性の姿になって野中の屋敷で男をもてなしました。この屋敷には12の部屋がありましたが、ある時女性は「実はもう一部屋あるのですが、そこには決して近づかないで下さい。」と言い置いて外出しました。そう言われるとなおさら近づきたくなるのが人の常。男が約束を破って13番目の部屋をのぞいてみると、一羽の鶯が一心に法華経を唱えていたのです。はっとした途端、屋敷は消えうせ、男は広い野原に立ち尽くしていたのでした。