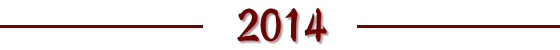鰯の頭も信心から
今でこそあまり捕れなくなって値段も高くなった鰯ですが、昔は何処でも大量に捕れた魚でした。すなわち鰯の頭のようなものでも、それを信じる人にとっては、大きな意味をもつという意味です。でも唐突に鰯の頭とは、どこからきたのでしょうか。答えは節分の行事です。昔は、豆をまく節分の夜に、悪鬼を退散させるおまじないとして、臭気を放つ鰯の頭を、葉にトゲのある柊(ひいらぎ)の枝にさして、戸口や窓にかけました。怖ろしい悪鬼がひとつふたつの鰯の頭で逃げ出す筈はないようなものですが、庶民は律儀に行っていました。また、同じ意味を持つ諺に「鰯の頭も観音様に見える」があります。
棒を願うて針
「針小棒大」は物事を大げさに言い立てる時に使われます。この「棒を願うて針」は大きな願いも現実には、針ほど、すなわちほんのわずかしか達成されないものだ、という意味です。だからこそ望みは大きく持てというのです。ところで、「針供養」は2月8日に行われます。折れたり錆びたりした針を、豆腐やコンニャクに刺して裁縫の上達を願う行事です。今でもこの行事を行う寺院があります。