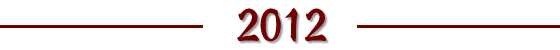3.七十二候を読み解く「 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)」
 3月5日は啓蟄。啓は開く、蟄とは巣籠もりの意味で、冬の間土中で冬ごもりをしていた爬虫類や両生類、昆虫がはい出してきます。そうした中で最も身近な存在はカエルでしょう。
3月5日は啓蟄。啓は開く、蟄とは巣籠もりの意味で、冬の間土中で冬ごもりをしていた爬虫類や両生類、昆虫がはい出してきます。そうした中で最も身近な存在はカエルでしょう。
やかましくカエルが鳴くさまを昔から蛙合戦といい、多くのカエルが集まって相戦うとされていましたが、これはもちろん雄が雌を呼ぶ声です。日本産のカエルは三十種ほどですが、世界には三千五百種ものカエルが生息しており、食用の蛙もあります。水田に住むトノサマガエル、雨を知らせるというアマガエル、美声を響かせるカジカガエルなどがよく知られますが、ことにヒキガエルは住宅地にも住みついているので、都市の住民にもおなじみです。
カエルは古くから人間と関わってきたようで、古墳時代に作られた銅鐸には、カエルがしばしば描かれています。これは我々が農耕民族であることと関係があるようです。農耕で大切なのは太陽と水です。ですから、カエルのほかにもカメ、トンボなどいずれも水に縁がある動物の絵が描かれています。
中世の鳥羽僧正作と伝えられる「鳥獣戯画」には踊るカエルがユーモラスな筆致で描かれていますが、インドのバラモン教の聖典やヨーロッパの童話にもしばしば登場して怪異でしかもユーモラスな存在感を示します。グリム童話「カエルの王様」はご存じの方も多いでしょう。チャッキリ節では「蛙が鳴くんで雨ずらよ」と歌われますが、カエルは気圧の変化に敏感なのだそうです。