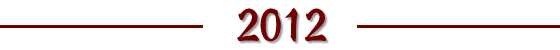4.七十二候を読み解く「玄鳥至(つばめ きたる)」
 4月5日は燕が南の国から渡って来る日。よく、燕が低く飛べば雨、高く飛べば晴れといいますが、燕は雨で濡れた土に枯れ草を混ぜて巣を作るので、そうした様を古人が観察したことによる言い伝えと思われます。
4月5日は燕が南の国から渡って来る日。よく、燕が低く飛べば雨、高く飛べば晴れといいますが、燕は雨で濡れた土に枯れ草を混ぜて巣を作るので、そうした様を古人が観察したことによる言い伝えと思われます。
燕は、白鳥や雁とともに代表的な渡り鳥ですが、その習性を科学的に知らなかった昔の人は、不老不死の楽土である常世の国から、季節がめぐると当地に飛来すると考えました。このような考えは世界中にあり、燕が天から火を取ってきて人間に与えてくれたとか、燕が海底の泥を加えて地上に上り大地を作った、などという神話が伝えられています。すなわち燕は、この世と天界・水界を結ぶ鳥として捉えられてきたのです。
「竹取物語」でかぐや姫は、燕がお腹に持つという子安貝を所望します。子安とは安産のこと、子安貝の別名は八丈宝という巻き貝です。わが国では八丈島や小笠原諸島などに産し、昔、妊娠した女性は安産のお守りにしたといいます。
海岸の岩の間に住みついており、この話からも燕は水に縁がある鳥と考えられていたことが分かります。また燕は、巣の中に貝を残しておくという言い伝えもあり、その貝も安産のお守りになるといわれています。
さらに燕は、農耕生活を送る人々にとって害虫を捕食する益鳥であったため、渡来は喜ばしいことでした。いろいろな言い伝えをもつ燕ですが、それは巣を山奥ではなく家の軒下に作ることからきているのでしょう。