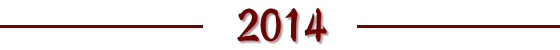流れに枕し、石に漱ぐ
 負け惜しみが強く、こじつけがうまいことをさします。「枕流漱石(ちんりゅうそうせき)」とも言います。
負け惜しみが強く、こじつけがうまいことをさします。「枕流漱石(ちんりゅうそうせき)」とも言います。
出典は中国の故事で、深山幽谷に分け入り、山中で石を枕に眠り、渓谷の流れで口を洗う隠遁生活を望んだ孫楚が「石に枕し、流れに漱ぐ」というべきなのを「流れに枕し、石に漱ぐ」と言い間違ったところ、友人の王済に笑われ、そのことがよほど口惜しかったのか、「枕流は耳を洗うため、漱石は歯を磨きあげるためさ」と話を何とかこじつけました。これを聞いていた人々は、「孫楚のこじつけのうまさはさすがだ」と感心したと言います。「流石」を「さすが」と読ませるのもこの故事からきています。
また、明治の文豪・夏目漱石(本名・金之助 ) がこの故事にちなんで雅号にしたことでも有名です。
立てば芍薬、座れば牡丹
美人の姿を花に見立てたもの。次に「歩く姿は百合の花」と続きます。いずれも初夏の花で、それぞれの特徴をとらえた表現です。芍薬は牡丹より少し遅れて花をつけます。華麗で品格の高い大輪の牡丹が「百花の王」と呼ばれるのに対して、芍薬には「花の宰相」の名があります。二つとも中国原産で元々は薬用として渡来しました。