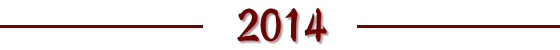出藍の誉れ
「青は藍より出でて藍より青し」のこと。中国戦国時代の荀子(じゅんし)の言葉で、青色の染料は藍の葉から作るが、もとの葉の色よりも美しいという意味。教えを受けた生徒が先生よりすぐれている時のたとえです。
「藍(あい)」は青色の染料を作るために、古くから栽培されたタデ科の一年草。紅色か白色の小さな花が穂のように密生して咲き、6月頃に刈り取ります。藍玉を水で溶いた藍汁をかき混ぜ、染料として仕上げる時に、紺色の泡がまとまって花のように見えるところから「藍の出花」は、年頃の女性の美しいさまをさします。
洞が峠をきめこむ
主君織田信長を京都本能寺で討った明智光秀と、羽柴(豊臣)秀吉が京都・山崎の天王山で戦ったのは1582年6月13日。秀吉が勝ったこの合戦がその後の歴史の流れを決定したところから「天下分け目の天王山」と呼ばれます。この時、近くの洞が峠で戦いの形勢を眺めていたのが信長の家臣だった武将・筒井順慶。勝負がはっきりしてから秀吉側につきました。このように二股をかけて「日和見主義的」な行動をさした言葉です。

君子曰、学不可以已。青取之於藍、而青於藍。冰水為之、而寒於水。
(書き下し)
君子(くんし)曰(いわ)く、学は已(や)むべからず。
青(あお)は之(これ)を藍(あい)より取れども、藍よりも青し。
冰(こおり)は水(みず)之(これ)を為(な)せども、水よりも寒(つめ)たし。
(語注)
○君子 :学問を修めた立派な人。人格者。
○藍 :タデ科の一年草。染料をつくるもとになる。
(現代語訳)
ある立派な方がこう言われた。「学問は途中でやめてはいけない。
青の染料(せんりょう)は藍(あい)という草から取るが、
藍よりもいっそう鮮やかな青色になる。
氷は水からできるものだが、水よりもいっそう冷たくなる」と。
(学問も中断せずに続ければ、よりすぐれた成果をあげることができるのだ)