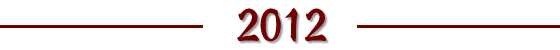7.七十二候を読み解く「蓮始開(はすはじめてひらく)」
 7月12日は蓮が咲き始める日。蓮とはハチスの略で、花の後、太くなった花軸の上部が蜂の巣のような形になるのでこの名があります。仏教のシンボルとして仏典に登場する蓮華は、蓮、水蓮の両方を指していますが、水蓮は水面に浮かんでおり、蓮は水面から突き出ているので見分けがつきます。インドの農村には多くの溜池があり、蓮や水蓮が美しく咲いているとのこと、蓮華はインドの国花でもあります。暑いインドでは熱を鎮める水は貴重で、その水の中から姿を現す蓮華は尊い美しさにあふれた花とされました。
7月12日は蓮が咲き始める日。蓮とはハチスの略で、花の後、太くなった花軸の上部が蜂の巣のような形になるのでこの名があります。仏教のシンボルとして仏典に登場する蓮華は、蓮、水蓮の両方を指していますが、水蓮は水面に浮かんでおり、蓮は水面から突き出ているので見分けがつきます。インドの農村には多くの溜池があり、蓮や水蓮が美しく咲いているとのこと、蓮華はインドの国花でもあります。暑いインドでは熱を鎮める水は貴重で、その水の中から姿を現す蓮華は尊い美しさにあふれた花とされました。
さらに仏典に「高原に生ぜず、汚泥から蓮華が生ずる如く、汚泥のような世間の中にこそ菩薩の生き方が示される。」という旨が述べられているように、菩薩の姿にも例えられます。インドの神話では、蓮華から神が現れて万物を創造したと伝えます。鑑真が日本に持ってきたものとして「青蓮華二十茎」の記載がありますが、青蓮華はしばしば清らかな目に例えられて称揚されました。
蓮は日本にも自生しており、奈良時代にはすでに食用にしていた記録が残っています。蓮根といいますが、実際は根ではなく地下茎です。
また蓮の種子の生命力はとても旺盛で、泥炭層では千年以上発芽力を保ち続けるといわれてきましたが、1951年、大賀一郎博士により、千葉市検見川の泥炭層から、二千年以上経過したと見られる古代ハスの種子が発見され、発芽に成功し開花しました。種子は1963年に中国各地にも送られ、武漢植物園では中国の古代蓮との交配がなされ「日中友誼蓮」が生み出されました。