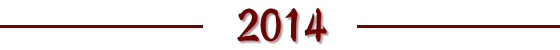地獄の釜の蓋があく
地獄の釜の蓋があく
江戸末期のしりとり歌に「閻魔(えんま)は盆とお正月」とあるように、正月と7月16日は、地獄の主神・閻魔大王の縁日。この日は「地獄の釜の蓋があく」日で、地獄の鬼たちが亡者を煮る行事を休み、釜の蓋があいたままになるといいます。 地獄では、現世で悪いことをした人間が、死後黄泉の閻魔の庁で大王の審判を受けると信じられています。この時、閻魔大王が持っているのが死者の生前の行いが書き込んである帳簿である「閻魔帳」です。でも我々は「エンマ帳」というと、学校の先生が生徒達の成績を記入しておくノートのことを想像しますよね。
稲光は豊作のしるし
適度なおしめりが稲には良いという農耕民族としての長い経験を踏まえた言葉です。雷を「稲妻」というのは、稲がひらめく電光と交わることで穂をつけるという古代人の信仰に基づきます。