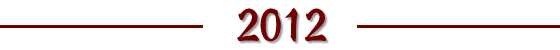8.七十二候を読み解く「寒 蝉 鳴(ひぐらしなく)」
8月18日はヒグラシの鳴く日。万葉の時代にはヒグラシが、蝉の総称だったといわれます。晩夏の頃、明け方と夕暮れにカナカナカナと何とも哀調帯びた鳴き声を聞かせるヒグラシ。日本人に愛されてきたのも当然でしょう。清少納言も「枕草子」の中で、ヒグラシを好ましい虫九種の一つに挙げています。
平安時代、琵琶と和歌の名手である盲目の音曲師に蝉丸と呼ばれた人物がいました。蝉の鳴き声が何よりも印象的だったことを示すものでしょう。小泉八雲は「日本瞥見記」に、ミンミンゼミの鳴き声の見事さを「僧侶の経を誦するが如し」と記しています。
わが国に生息する蝉の種類は多く、百種以上にも及びます。
「やがて死ぬ けしきは見えず蝉の声(芭蕉)」
蝉は、卵から羽化までの期間が非常に長く、四年から七年もかかります。それなのに成虫となってからの寿命はたった二週間。このはかなさを詠んだ句です。涼しげなヒグラシやツクツクボウシはもちろん、暑さが倍増するようなアブラゼミの声も、こうした生涯を思えば胸に迫ります。
空蝉とは蝉の脱け殻をいいますが、「現身」も「うつせみ」と読みます。空蝉と同音です。この世に生きている私たちの身も蝉もはかない存在に変わりはありません。けれども中国では、脱皮を重ねて姿を変えていく蝉を再生の象徴と見ることもあります。