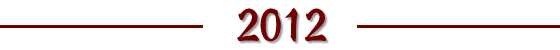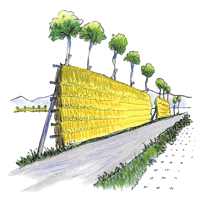 9.七十二候を読み解く「禾乃登(こくものすなわちみのる)」
9.七十二候を読み解く「禾乃登(こくものすなわちみのる)」
9月2日は禾乃登(こくものすなわちみのる)と中国の暦ではいっています。禾とは穀類の総称です。わが国への稲の伝来については諸説ありますが、山東半島から朝鮮半島を経て九州北部に伝わったとみられています。韓国語では米をサーリといい、日本でもシャリといったりしますが、サンスクリット語で米をシャーリというのに由来すると思われます。またお釈迦様の骨はシャリーラと呼ばれ、舎利と音写されることから、これに由来するという俗説もあります。
稲栽培の歴史は大変古く、ミャンマー(ビルマ)の紀元前一万年前の遺跡やタイの遺跡にも栽培の痕跡があります。お釈迦様の父・シュッドーダナは「清らかなお粥」という意味で、お米をかけがえのないものとする意識がうかがえます。これは日本人も同じで、わが国の美称が瑞穂の国、即ちみずみずしい稲穂の国ということからもわかるでしょう。本来は水生植物ですが、陸稲など、自然環境への適応力があり、しかも同じ面積の土地から小麦の二倍の収穫ができます。貯蔵が可能なことから米は財産化され、米持ちは地域の支配者となっていきました。そして米は日本人のサラリーとなり禄米と呼ばれました。米作りには水が欠かせません。灌漑技術を工夫することにより、日本人の科学的思考は発達したといわれています。
米は多くの国で豊穣の象徴とされ、ヒンズー教の儀式でも用いられます。
また西洋では結婚式を終えた二人に米を振りかけて祝福するのはおなじみの場面です。