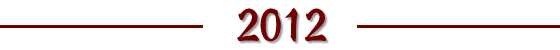10.七十二候を読み解く「山茶始開(つばきはじめてひらく)」
 11月7日はサザンカが咲き始める日。サザンカは漢字で書くと山茶花ですが、山茶(サンチャ)という語は中国・宗代の書物にひんぱんに見られ、ツバキを指しています。山に生えている茶の木に似た植物ということだったらしく、唐代の百科事典にも、サンチャの葉は茶に似ていると出ています。
11月7日はサザンカが咲き始める日。サザンカは漢字で書くと山茶花ですが、山茶(サンチャ)という語は中国・宗代の書物にひんぱんに見られ、ツバキを指しています。山に生えている茶の木に似た植物ということだったらしく、唐代の百科事典にも、サンチャの葉は茶に似ていると出ています。
さらに、サンチャは「海石榴(カイセキリュウ)」にも似ているとも書かれています。この海石榴を、日本では「古事記」や「風土記」でツバキと読ませているという、何ともややこしいことになっています。それというのも、茶もサザンカもツバキ科の植物であるため大変よく似ているのです。日本の茶の木は葉が小さいため、あまりツバキに似ているとも思えませんが、中国茶は葉が大きく、樹高も高いので紛らわしかったのでしょう。日本でも野性のサザンカは沖縄、奄美、九州、四国西南部に見られ、昭和32年、国の天然記念物に指定されました。
我々が現在、庭で目にするサザンカは、日本で産みだされた日本特有の花木です。
野性のものは白色だけですが、園芸種には紅、絞り、八重などが産みだされています。材質が固く裂けにくいので農具や大工道具の柄に用いられてきました。薪炭材としても優れており、種子からは食用油を採りました。
木ヘンに春の字の通り、春に先駆けて咲く椿に対して、「サザンカ、サザンカ咲いた道、たき火だ、たき火だ、落ち葉焚き」と歌われるように、寒さの日増しに加わる中、冬枯れの景色を彩る紅色はひときわ目をひきます。