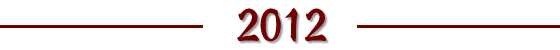12.乃 東 生(だいとうしょうず)
12.乃 東 生(だいとうしょうず)
12月22日は乃東生ず。「だいとうしょうず」と読みます。この日は冬至にも当たります。この時を境に北半球では昼間の時間が伸び始めるため、古くは冬至を年の始まりと考えました。
さて、ダイトウとは、ウツボグサのことです。シソ科の多年草で、北海道から沖縄まで、日当たりの良い山野や道端で普通に見られます。ウツボグサは、夏至の頃、他の植物がいよいよ勢いを増す時期に直立したまま穂が茶色くなって枯れ始めるために、夏枯草(かこそう)とも呼ばれます。反対に、ものみなじっと息をひそめる冬枯れの中、このウツボグサだけは青々と芽生え始めるというわけです。
靫(ウツボ)とは矢を入れて腰や背につける用具ですが、円柱形の穂の形がこれに似ていることからの命名です。六月、穂の下の方から紫色の花が咲き始めます。花筒の元に蜜があるため、昔の子どもは、花を抜き取って吸ったもので、吸花というのはここからきています。
これからは風邪が流行ってきますので、塩化カリウムを含むウツボグサの穂でうがい薬を作ってみましょう。8月初旬、褐色になり始めた穂を摘んで陰干しします。5〜10グラムに水300ミリリットルを加え、半量になるまで煎じたらでき上がり。
また、食間3回に分けて服用すれば利尿剤になりますが、妊娠している方は避けます。全草を陰干しして煎じると子供の疳に効くといわれ、カントリグサと呼ぶ地方もあります。